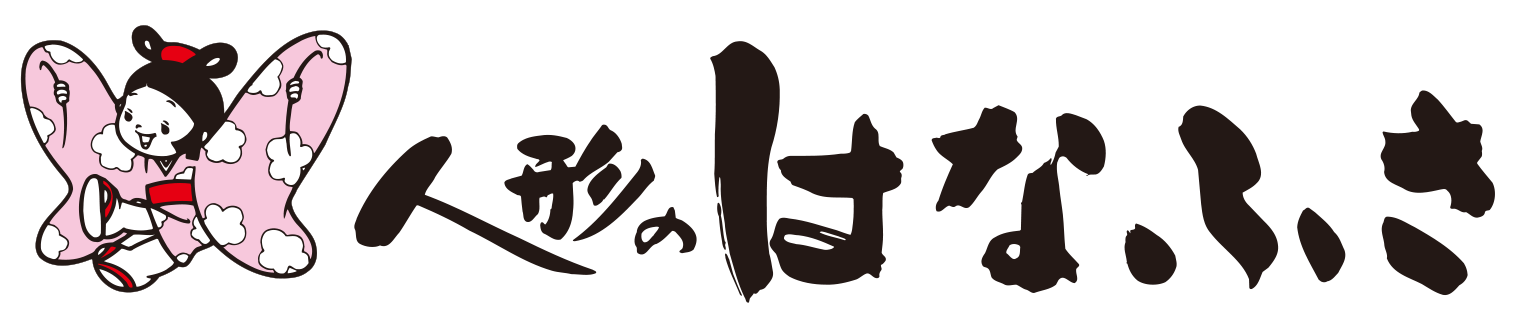はなふさの兜飾りが選ばれました
お知らせ
2025/08/17 10:00

七五三の意味や由来
七五三は、お子様の健やかな成長を神様に感謝し、将来の幸せと健康を祈る行事です。かつて医療や衛生環境が十分に整っていなかった時代、幼い子どもが無事に成長することは、決して当たり前のことではありませんでした。そのため、「七歳までは神の子」との言葉が残されているように、7歳を迎えるまでは神の加護にある存在として見守られていたのです。そのため、7歳になってようやく「この世の中に誕生した」お祝いを行っていたのです。
こうした背景の中で生まれたのが、「七五三」のお祝いです。平安時代には、子どもの成長に合わせた通過儀礼が行われていました。
3歳の「髪置き(かみおき)の儀」
-
5歳の「袴着(はかまぎ)の儀」
-
7歳の「帯解き(おびとき)の儀」
これらの儀式は、健やかな成長を神様に感謝し、これからの無事を祈る大切な行事でした。
やがて江戸時代になると、武家や裕福な町人の間でも広まり、明治時代には三つの節目をあわせて「七五三」と呼ばれるようになりました。今日では、誰もが子どもの健やかな成長を祝う日本の伝統行事として親しまれています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3歳の「髪置き(かみおき)の儀」
平安時代は男女ともに生まれて7日目に産毛を剃り、3歳になるまでは頭上に丸く髪を残す芥子坊などの髪型でした。そして3歳の春を迎えると髪を伸ばし始める風習がありました。その際に「髪置き(かみおき)の儀」が行われ、産みの親以外で長寿や子宝に恵まれた人に儀式上の親になってもらい、白髪頭になるまで長生きするようにと長寿を祈りました。
5歳の「袴着(はかまぎ)の儀」
五歳の男児が初めて袴をはく儀式をいいます。
子どもを基盤の上に立たせて袴親(儀式上の親)が裃(かみしも)をつけるという作法がありました。基盤は「勝負の場」の象徴として用いており、この子が大きくなって出会うであろう人生での様々な「勝負の場」で四方を制するという意味が込められています。現代でも宮中では古式にのっとった「袴着の儀」が行われています。
7歳の「帯解き(おびとき)の儀」
七歳の女児が着物に付いている付け紐を取って初めて本式の帯を締める儀式をいいます。帯は「魂をその内にしっかりとどめておく」という意味があり、帯を締めることにより「身をもちくずすことのないように」という願いが込められています。
ひもおとしってなあに?
山陰地方は七五三のことを「ひもおとし」と呼びます。
「ひもおとし」の語源は、生まれてすぐのお宮参りの祝い着には紐が付いていますが、その紐を取り、帯を締めて七五三参りをする風習に由来するといわれています。このひもおとしの行事を鳥取・島根の山陰地方では男の子も女の子も3歳で行う地域が多いです。これは全国的には男の子は5歳の「袴着の儀」、女の子は7歳の「帯解きの儀」で行うお祝いを早く行ってあげたいという子への親心から生まれた山陰地方の風習と言われています。